LANケーブルや電気コードをネズミから守るには?【プラスチック製の保護管が有効】4つの簡単な対策法

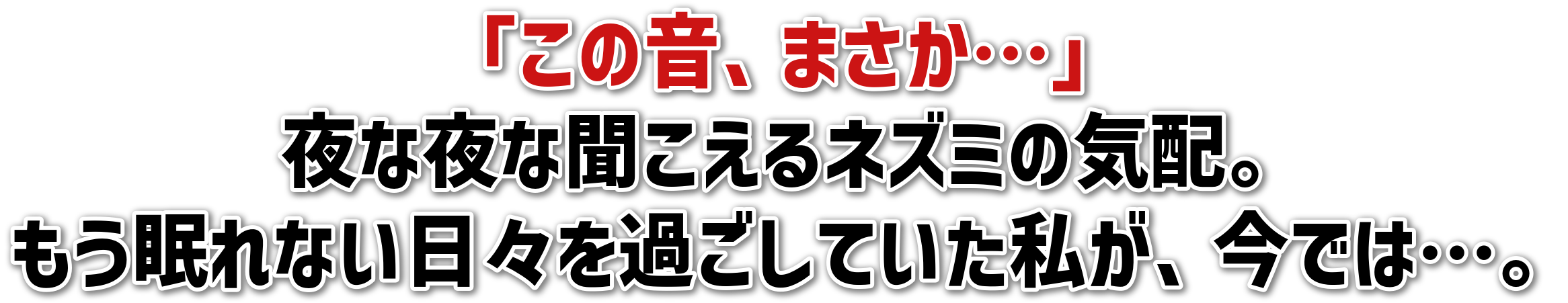
【この記事に書かれてあること】
ネズミによる配線被害、悩んでいませんか?- ネズミによる配線被害は月に1〜2回のペースで発生する可能性がある
- プラスチック製保護管を使用することで被害を90%以上防ぐことができる
- 保護管は硬度の高いポリカーボネート製で厚さ2mm以上のものを選ぶ
- コーヒーの粉やペパーミントオイルなど身近な材料でも効果的な対策ができる
- 超音波装置やLEDライトを活用することでネズミを寄せ付けない環境を作れる
実は、この問題、思った以上に深刻なんです。
月に1〜2回もの頻度で被害が起こる可能性があるんです。
でも、大丈夫。
適切な対策を取れば、90%以上の被害を防げるんです。
この記事では、プラスチック製保護管の驚くべき効果から、身近な材料を使った意外な対策法まで、10の画期的な方法をご紹介します。
ネズミから大切な配線を守り、安心して暮らせる家づくりのヒントが満載です。
さあ、一緒にネズミ対策の達人になりましょう!
【もくじ】
ランケーブルや電気コードをネズミから守る重要性
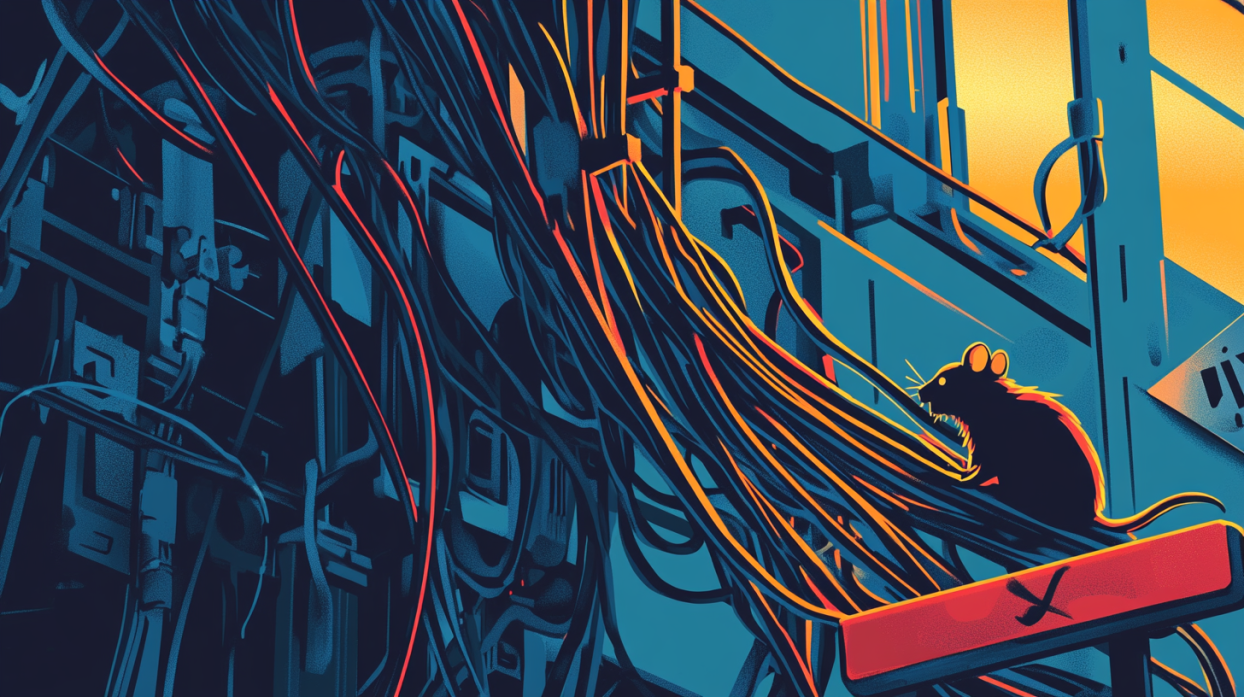
ネズミによる配線被害の深刻さ!被害の特徴を知ろう
ネズミによる配線被害は想像以上に深刻です。家電製品の故障や火災の危険性まであるんです。
ネズミが配線をかじると、まず目に見える被害として被覆の剥がれや断線が起こります。
「えっ、こんなに簡単に壊れちゃうの?」そう思うかもしれません。
でも、それだけじゃないんです。
露出した導線はショートの原因になります。
ジジッ、パチパチッという音と共に火花が散る様子を想像してみてください。
怖いですよね。
最悪の場合、火災につながる可能性もあるんです。
さらに、ネズミの被害は目に見えないところでも進行しています。
- 通信速度の低下
- 電気機器の誤作動
- 配線周辺の異臭
早めの対策が大切です。
「でも、うちはネズミなんていないよ」そう思っていても油断は禁物。
ネズミはわずか1センチの隙間があれば侵入できてしまうんです。
知らないうちに家の中に住み着いているかもしれません。
ネズミによる配線被害、あなたの家は大丈夫ですか?
次は、なぜネズミが配線をかじるのか、その意外な理由に迫ってみましょう。
ネズミが配線をかじる「意外な理由」に驚愕!
ネズミが配線をかじる理由、それは歯の健康維持なんです。意外ですよね。
ネズミの歯には驚くべき特徴があります。
なんと一生伸び続けるんです。
「えっ、それじゃあ口からはみ出しちゃわないの?」そう思いますよね。
でも、大丈夫。
ネズミには本能的に歯を摩耗させる習性があるんです。
硬いものをかじることで、伸びすぎた歯を削るわけです。
野生のネズミなら木の枝や石ころをかじります。
でも、家の中にいるネズミにとって、ちょうどいい硬さのランケーブルや電気コードは格好の"歯磨き道具"なんです。
ネズミの歯は驚くほど硬くて鋭いんです。
- 人間の歯の5.5倍の硬さ
- 1日に約0.4mm伸びる
- プラスチックや柔らかい金属も噛み切れる
「じゃあ、もっと硬い素材の配線にすればいいんじゃない?」そう考えるかもしれません。
でも、それだけでは不十分なんです。
ネズミは好奇心旺盛で、新しいものを見つけると必ずかじってみる習性があるからです。
ネズミにとって配線をかじるのは、生きるために必要な行動なんです。
だからこそ、私たち人間側が賢く対策を立てる必要があるんです。
次は、実際にどのくらいの頻度で被害が起こるのか、見ていきましょう。
配線被害の頻度は予想以上!月に1〜2回のペースも
配線被害の頻度、実は想像以上に高いんです。月に1〜2回のペースで発生することもあるんです。
「えっ、そんなにしょっちゅう?」そう思いますよね。
でも、これは決して珍しい話ではないんです。
ネズミが家に住み着いてしまえば、毎日のようにコードをかじる可能性があるんです。
ネズミの活動時間を考えてみましょう。
- 夜行性で、人間が寝ている間に活発に動く
- 1日に約20回も餌を探しに出てくる
- 1回の外出で約20〜30分活動する
季節によっても被害の頻度は変わってきます。
秋から冬にかけては特に要注意。
寒さを避けて家の中に入ってくるネズミが増えるからです。
この時期は被害が2倍以上に増えることも。
「うちは新築だから大丈夫」なんて油断は禁物です。
新築住宅でも、建材の隙間からネズミが侵入するケースがあるんです。
築年数に関係なく、どの家でも注意が必要なんです。
ネズミによる配線被害、もしかしたらあなたの家でも今まさに進行中かもしれません。
次は、被害の兆候を見逃さないためのサインについて詳しく見ていきましょう。
見逃し厳禁!配線被害の兆候「5つのサイン」
配線被害の兆候、見逃していませんか?早期発見のために、5つの重要なサインを覚えておきましょう。
まず1つ目は、かじられた跡です。
配線の表面がザラザラしていたり、小さな切れ込みがあったりしませんか?
これはネズミの歯形の可能性が高いんです。
「えっ、そんな小さな傷でも危険なの?」そう思うかもしれません。
でも、これが大事故の始まりになるかもしれないんです。
2つ目は、被覆の剥がれ。
配線の外側の覆いが剥がれて、中の銅線が見えていませんか?
これは危険信号です。
露出した導線は感電やショートの原因になります。
3つ目は、配線周辺のネズミの糞。
米粒のような小さな黒いツブツブを見つけたら要注意。
ネズミが活動した証拠です。
4つ目は、異臭。
配線周辺で焦げたような、または獣臭い匂いがしませんか?
これはネズミの尿や、配線の損傷による異臭かもしれません。
最後に5つ目、機器の誤作動です。
- インターネットの接続が不安定
- 電気製品がチカチカする
- ブレーカーがよく落ちる
これらのサインを見逃さず、早めに対策を取ることが大切です。
でも、間違った対策をしてしまうと、かえって事態を悪化させてしまうかもしれません。
次は、やってはいけない逆効果な対策について見ていきましょう。
配線むき出しはやっちゃダメ!被害を招く「逆効果な対策」
配線被害対策、実は逆効果になってしまうこともあるんです。絶対にやってはいけない対策をしっかり覚えておきましょう。
まず最大のタブーは、配線をむき出しのまま放置すること。
「見えるところにあれば、すぐに被害に気づけるでしょ」なんて考えていませんか?
でも、これが一番危険なんです。
ネズミにとっては、「さあ、どうぞかじってください」と誘っているようなものです。
次に注意したいのが、一般的な粘着テープでの保護。
「とりあえずガムテープを巻いておけば大丈夫」なんて思っていませんか?
実はこれ、逆効果なんです。
ネズミは粘着テープの材質が大好き。
かえってかじる対象として注目されてしまうんです。
他にも、よくある間違った対策をいくつか挙げてみましょう。
- 香り付きのスプレーを吹きかける(刺激的な匂いに興味を引かれる)
- 柔らかい布で包む(巣作りの材料として使われる)
- 配線を床に這わせる(ネズミの通り道になってしまう)
大丈夫、効果的な対策はたくさんあるんです。
例えば、硬質プラスチック製の保護管を使うのが効果的。
ネズミの歯でも簡単にはかじれない硬さがポイントです。
また、金属製のメッシュカバーを使うのも良い方法。
通気性もあって、配線の熱がこもる心配もありません。
配線被害対策、正しい方法で行うことが大切です。
間違った対策で被害を拡大させてしまわないよう、注意しましょう。
プラスチック製保護管で効果的に配線を守る方法

プラスチック製保護管の驚くべき効果!被害を90%以上防ぐ
プラスチック製保護管を使えば、ネズミによる配線被害を90%以上も防げるんです。すごいですよね。
「え?そんなに効果があるの?」って思った方も多いはず。
でも本当なんです。
プラスチック製保護管は、ネズミ対策の救世主とも言えるんです。
なぜそんなに効果があるのか、理由を見ていきましょう。
- ネズミの歯が立ちにくい硬さ
- 滑りやすい表面でかじりにくい
- 配線全体を覆って守れる
ネズミの歯は鋭いですが、硬いプラスチックには歯が立たないんです。
「カリカリ」と音はするかもしれませんが、中の配線まで届くことはありません。
さらに、プラスチック製保護管の表面は滑らかです。
ネズミがかじろうとしても、歯がツルッと滑ってしまうんです。
まるで氷の上を歩くようなもの。
ネズミにとっては、とってもストレスフルな体験になるわけです。
「でも、隙間から入り込まれたらダメじゃない?」そう思った方、鋭い洞察力です!
でも大丈夫。
正しく設置すれば、隙間なく配線全体を守れるんです。
ただし、注意点もあります。
安物の薄いプラスチック管では効果が薄いんです。
選び方が重要なんです。
どう選べばいいのか、次の項目で詳しく見ていきましょう。
保護管選びの極意!硬度と厚さがカギを握る
プラスチック製保護管選びで最も重要なのは、硬度と厚さなんです。この2つがカギを握っています。
まず硬度について。
「硬ければ硬いほど良い」と思うかもしれません。
でも、そうでもないんです。
硬すぎると設置が難しくなっちゃうんです。
適度な硬さが大切なんです。
理想的なのは、ポリカーボネート製の保護管。
このポリカーボネートという素材、すごいんです。
- 高い耐衝撃性
- 適度な柔軟性
- 耐熱性も優秀
簡単に言うと、とっても丈夫なプラスチックのことです。
防弾ガラスにも使われる素材なんです。
そう聞くとすごさが伝わりますよね。
次に厚さ。
これも重要です。
2ミリ以上の厚さがあるものを選びましょう。
「2ミリってどのくらい?」と思った方、5円玉くらいの厚さをイメージしてください。
薄すぎると、ネズミに噛み切られる可能性があります。
逆に厚すぎると、設置が大変になっちゃいます。
2ミリ以上というのが、ちょうどいいバランスなんです。
色も選ぶポイントです。
透明なものを選ぶと、中の配線の状態が見えやすくなります。
「あれ?ここが変色してる?」なんて異変にも気づきやすいんです。
値段の安いものに飛びつくのは禁物です。
「安物買いの銭失い」なんて言葉がありますよね。
保護管選びにもピッタリ。
多少高くても、品質の良いものを選ぶことが大切です。
さあ、理想の保護管が見つかったら、次は正しく設置することが重要です。
設置方法について、次の項目で詳しく見ていきましょう。
保護管の正しい設置方法!隙間と固定部分に要注意
プラスチック製保護管を効果的に使うには、正しい設置方法が重要です。特に注意すべきは、隙間と固定部分なんです。
まず、隙間について。
「ちょっとくらいの隙間なら大丈夫でしょ?」なんて思ってませんか?
それが大間違い。
ネズミは1センチの隙間さえあれば侵入できてしまうんです。
信じられないかもしれませんが、本当なんです。
では、どうやって隙間をなくすのか。
コツをいくつか紹介しましょう。
- 保護管同士の接続部分をしっかり密着させる
- 曲がり角ではエルボー(L字型の部品)を使う
- 端部はエンドキャップでしっかり封をする
ホームセンターで保護管を買うときに、一緒に売っているパーツです。
店員さんに聞けば教えてくれますよ。
次に固定部分。
これも重要なポイントです。
保護管をしっかり固定しないと、ネズミに押し倒されちゃうかもしれません。
そうなると、せっかくの対策が台無しです。
固定には専用のクリップを使いましょう。
30センチから50センチおきに取り付けるのがおすすめです。
「そんなにたくさん付けるの?」って思うかもしれません。
でも、これくらいしっかり固定しないと、ネズミの力に負けちゃうんです。
壁に穴を開けるのが難しい場合は、強力な両面テープを使うのも一つの手です。
ただし、経年劣化で剥がれる可能性があるので、定期的なチェックを忘れずに。
最後に、配線の出入り口にも注意が必要です。
ここが弱点になりがちなんです。
保護管の端をコの字型に曲げて、配線が露出しないようにしましょう。
「えっ、そこまでやるの?」って思った方もいるかもしれません。
でも、ここまでやって初めて、90%以上の効果が得られるんです。
面倒くさいかもしれませんが、がんばって設置しましょう。
きっと素晴らしい結果が待っていますよ。
金属製保護管vsプラスチック製保護管!選ぶべきなのは?
金属製とプラスチック製、どちらの保護管を選ぶべきか悩んでいませんか?結論から言うと、多くの場合はプラスチック製がおすすめです。
「えっ?金属の方が丈夫そうなのに」そう思った方も多いはず。
確かに一見そう見えますよね。
でも、実はそうでもないんです。
それぞれの特徴を比べてみましょう。
- 金属製:重い、高価、錆びる可能性あり
- プラスチック製:軽い、比較的安価、錆びない
でも、重いんです。
「重いのがどうして問題なの?」って思いますよね。
実は、重いと設置が大変なんです。
天井裏や壁の中に這わせるのが一苦労。
DIYでやろうと思ったら、腰を痛めちゃうかも。
それに、金属製は高価です。
「お金かけた方がいいでしょ?」なんて思うかもしれません。
でも、必要以上にお金をかける必要はありません。
プラスチック製でも十分な効果が得られるんです。
さらに、金属製には錆びるリスクがあります。
「え?室内なのに?」って驚くかもしれません。
でも、湿気の多い場所では十分あり得るんです。
錆びると、見た目が悪くなるだけでなく、保護効果も下がっちゃいます。
一方、プラスチック製は軽くて扱いやすい。
DIYが得意じゃない人でも、比較的簡単に設置できるんです。
値段も手頃で、錆びる心配もありません。
ただし、プラスチック製にも弱点はあります。
紫外線に弱いんです。
「室内なら関係ないでしょ?」って思うかもしれません。
でも、窓際に設置する場合は要注意。
長年の日光で劣化する可能性があります。
そんな時は、紫外線カット機能付きのプラスチック製保護管を選びましょう。
少し値は張りますが、長持ちする分、結局はお得です。
結局のところ、ほとんどの家庭ではプラスチック製で十分。
金属製が必要なのは、工場など特殊な環境くらいです。
あなたの家でネズミ対策をするなら、プラスチック製保護管で決まりですね。
身近な材料で代用できる!アルミホイルの意外な効果
プラスチック製保護管を買う時間がない!そんな時は、アルミホイルで応急処置ができちゃうんです。
意外でしょ?
「えっ?アルミホイル?あの料理に使うやつ?」そう思った方、正解です。
キッチンにあるアレです。
でも、ネズミ対策にも使えるんです。
すごいでしょ?
アルミホイルがネズミ対策に効果的な理由、いくつかあるんです。
- ネズミが嫌う金属の味がする
- 噛むと歯にキーンとくる不快な感覚がある
- ガサガサした音がネズミを怖がらせる
配線にアルミホイルを何重にも巻きつけるだけ。
「えっ、それだけ?」って思うでしょ。
でも、本当にそれだけなんです。
ただし、注意点もあります。
アルミホイルは薄いので、何重にも巻くことが大切。
「めんどくさいなぁ」って思うかもしれません。
でも、手を抜くと効果が半減しちゃうんです。
がんばって巻きましょう。
それから、定期的な点検も忘れずに。
アルミホイルは破れやすいので、1週間に1回くらいチェックするのがいいでしょう。
「そんなに頻繁に?」って思うかもしれません。
でも、小まめなチェックが大切なんです。
アルミホイルの他にも、身近な材料でネズミ対策ができます。
例えば、新聞紙を細長く丸めて、それを何本も束ねて配線に巻きつける方法も。
「新聞紙?それって効果あるの?」って疑問に思うかもしれません。
でも、意外と効果があるんです。
ネズミは新聞紙の匂いが苦手みたいです。
もちろん、これらはあくまで応急処置。
長期的にはやっぱりプラスチック製保護管を使うのが一番です。
でも、今すぐ何とかしたい!
という時には、アルミホイルや新聞紙で対応してみてください。
思わぬところに解決策があるもの。
家にあるものでネズミ対策、意外と楽しいかもしれませんよ。
驚きの裏技!5つの画期的なネズミ対策で配線を守る

コーヒーの粉で配線を守る!カフェインの忌避効果とは
コーヒーの粉を使えば、ネズミから配線を守れるんです。意外でしょ?
「えっ?コーヒーの粉でネズミ対策?」そう思った方、多いはず。
でも、本当なんです。
コーヒーの粉に含まれるカフェインが、ネズミを寄せ付けない効果があるんです。
使い方は簡単。
コーヒーの粉を配線の周りに撒くだけ。
「それだけ?」って思いますよね。
でも、これがびっくりするほど効果的なんです。
なぜコーヒーの粉が効くのか、理由を見ていきましょう。
- ネズミはカフェインの匂いが苦手
- 粉の感触がネズミの足に不快感を与える
- コーヒーの苦味がネズミを遠ざける
ネズミは嗅覚が鋭いんです。
人間の1000倍以上の嗅覚を持っているんだとか。
だから、コーヒーの強い香りがネズミにとっては「うわっ、くさい!」って感じなんでしょうね。
ただし、注意点もあります。
コーヒーの粉は湿気を吸いやすいんです。
湿気たコーヒーの粉は効果が薄れちゃいます。
だから、1週間に1回は新しい粉に交換するのがおすすめです。
「でも、コーヒーの粉を撒くと部屋が汚れない?」そんな心配も無用です。
小皿に入れて置いておけば、散らかる心配もありません。
コーヒーの粉、意外とすごい効果があるんです。
しかも、家にある物で簡単にできる対策。
試してみる価値は十分にありますよ。
ペパーミントオイルの威力!ネズミを寄せ付けない香りの秘密
ペパーミントオイルは、ネズミを寄せ付けない強力な天然忌避剤なんです。驚きの効果があるんですよ。
「え?ハッカ油のこと?」そう思った方、鋭い!
ペパーミントオイルはハッカ油の一種なんです。
でも、普通のハッカ油よりも効果が強いんです。
なぜペパーミントオイルがネズミに効くのか、理由を見ていきましょう。
- 強烈な香りがネズミの嗅覚を刺激する
- メントールの清涼感がネズミに不快感を与える
- ネズミの神経系に作用して混乱させる
ペパーミントオイルを染み込ませた布を、配線の近くに置くだけ。
「それだけ?」って思いますよね。
でも、これがすごく効くんです。
ただし、原液のまま使うのは避けましょう。
強すぎて逆効果になることも。
水で10倍に薄めて使うのがおすすめです。
「10倍に薄める?計算面倒くさそう...」なんて思った方、大丈夫。
水1カップにペパーミントオイル10滴を入れれば、ちょうどいい具合になります。
効果は約2週間続きます。
「2週間もつの?長持ちするじゃん!」そう思いますよね。
でも、2週間経ったら忘れずに交換しましょう。
効果が薄れてきたころにネズミが戻ってくる可能性があるんです。
ペパーミントオイル、実はすごい味方なんです。
香りも爽やかだし、人間にも心地よい。
ネズミ対策しながら、お部屋の空気も良くなる。
一石二鳥ですね。
猫砂の意外な使い方!ネズミを警戒させる天敵の匂い
使用済みの猫砂、実はネズミ対策に意外な効果があるんです。驚きですよね。
「えっ?猫砂?あの猫のトイレに使うやつ?」そう、その通り。
捨てようと思っていた猫砂が、実は宝の山だったんです。
なぜ猫砂がネズミ対策に効くのか、理由を見ていきましょう。
- 猫の尿の匂いがネズミに危険を感じさせる
- ネズミの天敵である猫の存在を匂いで感じ取る
- 猫砂の粒子がネズミの足跡を残しやすくする
使用済みの猫砂を小さな容器に入れて、配線の近くに置くだけ。
「それだけ?簡単すぎない?」って思うかもしれません。
でも、これが意外と効果的なんです。
ただし、注意点もあります。
猫砂を直接床に撒くのはNGです。
掃除が大変になっちゃいます。
小さな容器や布袋に入れて使いましょう。
効果は約1週間続きます。
「1週間か...短いな」って思うかもしれません。
でも、1週間ごとに交換するのが理想的なんです。
新鮮な猫の匂いが、より効果的にネズミを寄せ付けないんです。
「でも、猫を飼ってないよ...」って方、心配いりません。
ペットショップで売っている未使用の猫砂でも、ある程度の効果があります。
ネズミは猫砂の粒子の感触も苦手なんです。
猫砂、意外な使い道があったんですね。
ネズミ対策に悩んでいる猫の飼い主さん、ぜひ試してみてください。
一石二鳥どころか、三鳥くらいの効果があるかもしれませんよ。
超音波でネズミを撃退!人間には聞こえない高周波の効果
超音波装置、実はネズミ対策の強力な味方なんです。人間には聞こえない音で、ネズミを撃退できちゃうんです。
「え?音で撃退?そんなことできるの?」って思いますよね。
でも、本当なんです。
ネズミの耳には聞こえる高周波音を出して、ネズミを寄せ付けないんです。
なぜ超音波がネズミに効くのか、理由を見ていきましょう。
- ネズミの聴覚は人間よりもはるかに敏感
- 高周波音がネズミにストレスを与える
- 音の方向を変えられず、逃げ場を失う
コンセントに差し込むだけ。
「えっ、それだけ?」って驚くかもしれません。
でも、本当にそれだけなんです。
24時間稼働させれば、常にネズミを寄せ付けない環境が作れます。
ただし、注意点もあります。
壁や家具で音が遮られると効果が薄れます。
だから、なるべく障害物のない場所に設置するのがポイントです。
効果範囲は約30平方メートル。
「うちの家全部には足りないな...」って思う方もいるかもしれません。
そんな時は、複数台設置するのがおすすめです。
「でも、ペットがいるんだけど大丈夫?」って心配な方もいるでしょう。
安心してください。
多くの超音波装置は、犬や猫には影響がないように設計されています。
ただ、ハムスターなどの小動物には影響があるかもしれないので、注意が必要です。
超音波装置、目に見えない音でネズミを撃退。
なんだか未来的な感じがしませんか?
静かに、でも確実にネズミ対策ができる。
試してみる価値は十分にありますよ。
青色光でネズミを寄せ付けない!LEDライトの活用法
青色のLEDライト、実はネズミ対策に意外な効果があるんです。光でネズミを寄せ付けない、なんだかすごいでしょ?
「え?青い光?なんでそんなのがネズミに効くの?」って思いますよね。
実は、ネズミは青色光が苦手なんです。
人間の目にはきれいに見える青色が、ネズミにとっては不快なんです。
なぜ青色光がネズミに効くのか、理由を見ていきましょう。
- ネズミの目は青色光に敏感
- 青色光が昼間のような錯覚を与える
- 光の点滅がネズミにストレスを与える
青色のLEDライトを配線の近くに設置するだけ。
「それだけ?簡単すぎない?」って思うかもしれません。
でも、これがびっくりするほど効果的なんです。
ただし、注意点もあります。
ずっと点けっぱなしにするのはおすすめしません。
電気代がかさむし、人間の目にも良くありません。
タイマーを使って、夜間だけ点灯させるのがコツです。
効果は即座に表れます。
「えっ、そんなに早いの?」って驚くかもしれません。
でも、本当なんです。
ネズミは光に敏感だから、すぐに効果が出るんです。
「でも、青い光って気分悪くならない?」なんて心配する方もいるでしょう。
大丈夫です。
最近のLEDライトは、人間の目に優しい青色を出せるんです。
寝室に置いても、ぐっすり眠れますよ。
青色LEDライト、意外とすごい効果があるんです。
しかも、見た目もおしゃれ。
ネズミ対策しながら、お部屋のインテリアも素敵に。
一石二鳥ですね。
ぜひ試してみてください。