ネズミによる漏電の危険性と対策は?【年間1000件以上の火災事故】予防と早期発見の3つのポイント

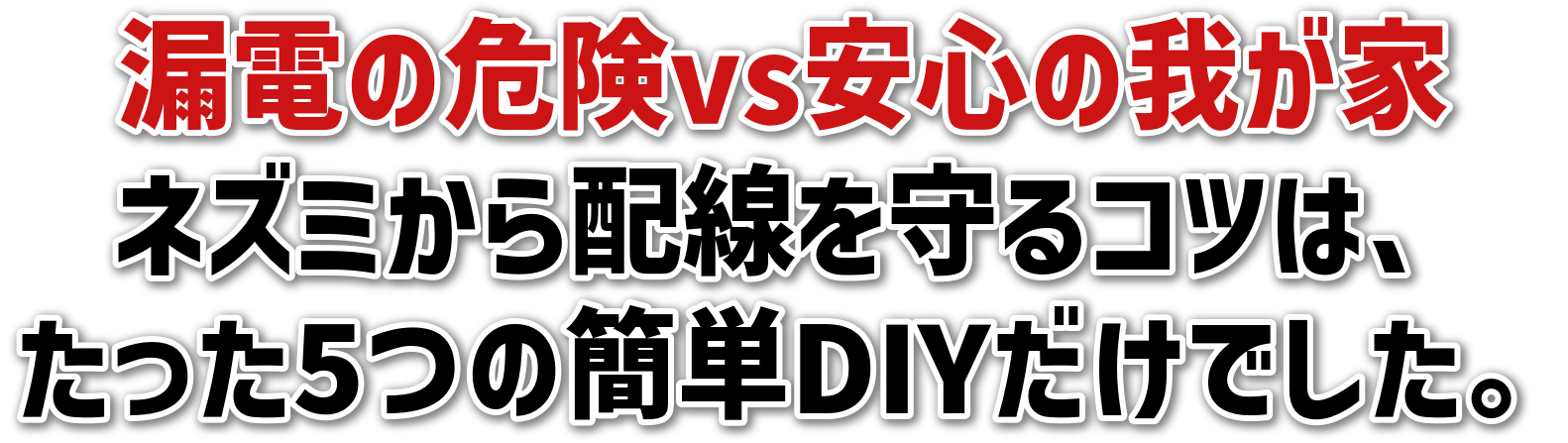
【この記事に書かれてあること】
ネズミによる漏電、その危険性をご存知ですか?- ネズミによる漏電は年間1000件以上の火災事故を引き起こす
- 電線の被覆をかじる習性がネズミによる漏電の主な原因
- 古い配線は新しい配線の10倍以上被害を受けやすい
- 電線保護管の設置がネズミからの配線保護に効果的
- 漏電遮断器の設置で電気火災のリスクを大幅に軽減
- ペパーミントやアルミホイルを使った簡単DIY対策で予防可能
実は、年間1000件以上もの火災事故を引き起こしているんです。
「えっ、そんなに多いの?」と驚かれるかもしれません。
でも、安心してください。
この記事では、ネズミによる漏電から我が家を守る方法をご紹介します。
電線保護管の設置から、意外な日用品を使ったDIY対策まで、すぐに実践できる予防法が満載です。
家族の安全を守るため、一緒に対策を学んでいきましょう。
【もくじ】
ネズミによる漏電の危険性と原因

年間1000件以上!ネズミが引き起こす火災事故の実態
ネズミによる漏電が原因の火災事故は、年間1000件以上も発生しています。これは驚くべき数字です。
「えっ、そんなにあるの?」と思われるかもしれません。
でも、実はネズミは私たちの想像以上に危険な存在なんです。
ネズミが引き起こす火災事故の実態を見てみましょう。
- ネズミが電線をかじることで、露出した導線から火花が散る
- 壁の中や天井裏で漏電が起こり、気づかないうちに火災に発展
- 特に古い家屋では、配線の劣化と相まって被害が大きくなる
実は、多くの家庭がこの危険にさらされているんです。
ネズミによる火災は、ジリジリ…パチパチ…と音を立てながら静かに始まります。
そして、気づいたときにはもう手遅れ。
「あれ?焦げ臭くない?」と思ったときには、すでに火の手が上がっているかもしれません。
だからこそ、事前の対策が重要なんです。
「でも、どうすればいいの?」そう思った方、大丈夫です。
この記事を読み進めれば、きっと対策方法が見つかるはずです。
ネズミから家族と家を守るために、一緒に学んでいきましょう。
電線被覆をかじる習性!ネズミが漏電を引き起こすメカニズム
ネズミが電線の被覆をかじるのは、彼らの本能的な習性なんです。でも、なぜそんな危険な行動をとるのでしょうか?
まず、ネズミの歯の特徴を知る必要があります。
ネズミの前歯は、一生伸び続けるんです。
「えっ、伸び続ける?」そう、まるで爪のように。
だから、ネズミは常に何かをかじって歯を削る必要があるんです。
電線の被覆は、ネズミにとって絶好のかじり物なんです。
- 適度な硬さで歯を削りやすい
- 細長い形状が口にフィットする
- 家の中のあちこちにあるので見つけやすい
そして、露出した銅線同士が接触すると…ビリビリッ!
漏電の始まりです。
「でも、すぐに火事になるわけじゃないよね?」その通りです。
最初は小さな火花程度かもしれません。
しかし、時間が経つにつれて被害は大きくなっていきます。
特に注意が必要なのは、目に見えない場所での漏電です。
壁の中や天井裏でじわじわと進行する漏電は、気づいたときには大変なことになっているかもしれません。
ネズミの習性を知ることで、私たちは効果的な対策を立てることができます。
「よし、これで対策の方向性が見えてきた!」そんな気持ちになってきませんか?
次は、具体的な予防法を見ていきましょう。
電気火災の恐ろしさ!通常の3倍のスピードで延焼する危険性
電気火災は、普通の火災とは比べものにならないほど恐ろしいものなんです。なんと、通常の火災の3倍ものスピードで燃え広がるんです。
「えっ、そんなに速いの?」と驚かれるかもしれません。
でも、これが電気火災の怖いところなんです。
なぜこんなに速く燃え広がるのでしょうか?
その理由を見ていきましょう。
- 電気は建物中の配線を通っているので、火の回る経路が多い
- 電気による発火は高温で、瞬時に周囲のものに燃え移る
- 電気は目に見えないので、火元の特定が難しく初期消火が遅れる
普通の火事なら、「あっ!」と気づいてすぐに消火器で消せるかもしれません。
でも、電気火災の場合は違うんです。
気づいたときには、すでに壁の中を通る配線を伝って2階まで燃え広がっているかもしれません。
「ギャー!どうしよう!」そんな状況になる前に、対策を立てておく必要があるんです。
電気火災の恐ろしさを知ったからこそ、私たちにできることがあります。
それは、日頃からの備えと早期発見です。
「じゃあ、具体的に何をすればいいの?」という声が聞こえてきそうですね。
大丈夫です。
次の項目で、効果的な対策方法をお伝えしていきます。
あなたの大切な家族と家を守るために、一緒に学んでいきましょう。
古い配線vs新しい配線!被害リスクに10倍以上の差
古い配線と新しい配線では、ネズミによる被害のリスクに大きな差があるんです。なんと、古い配線は新しい配線の10倍以上も被害を受けやすいんです。
「えっ、そんなに違うの?」と驚かれるかもしれません。
でも、これが現実なんです。
では、なぜこんなに大きな差が生まれるのでしょうか?
古い配線と新しい配線の違いを見てみましょう。
- 古い配線:被覆が劣化して柔らかくなり、ネズミが噛みつきやすい
- 新しい配線:被覆が丈夫で、ネズミの歯が立ちにくい
- 古い配線:絶縁性能が低下し、少しの損傷でも漏電しやすい
- 新しい配線:高い絶縁性能を持ち、多少の損傷では漏電しにくい
「うちの家、建ててから20年以上経つけど…」そう思った方、要注意です。
家の年齢と共に、配線も年をとっているんです。
でも、心配しないでください。
古い配線だからといって、すぐに全部取り替える必要はありません。
できることから始めればいいんです。
例えば、目に見える部分の配線から少しずつ新しいものに交換していく。
または、電気工事士さんに相談して、重要な箇所だけでも新しい配線に変えてもらう。
そんな方法もあります。
大切なのは、「うちの配線、大丈夫かな?」と意識することです。
気づくことが、安全への第一歩なんです。
古い配線を甘く見ず、できることから対策を始めていきましょう。
あなたの家族の安全は、あなたの手にかかっているんです。
応急処置は逆効果!電線の露出部分にテープを巻くのはNG
電線の露出部分を見つけたとき、「とりあえずテープを巻いておこう」と思いがちです。でも、これは大きな間違い。
むしろ逆効果なんです。
なぜテープを巻くのがダメなのか、その理由を見ていきましょう。
- テープは簡単にはがれてしまい、長期的な保護にならない
- テープの下で湿気がたまり、腐食が進行しやすくなる
- テープを巻いた部分が膨らみ、かえってネズミの注意を引く
- プロの修理が必要な問題を見過ごしてしまう可能性がある
でも、これが現実なんです。
テープを巻いた電線は、一見安全に見えるかもしれません。
でも、その下では「ジワジワ…」と危険が進行しているんです。
例えば、テープの下で湿気がたまると、そこから「サビサビ…」と腐食が始まります。
そして、知らないうちに電線がボロボロになってしまうんです。
また、テープを巻いた部分は少し膨らみます。
すると、好奇心旺盛なネズミにとっては「これ、なんだろう?」と興味をそそる対象になってしまうんです。
結果として、「ガジガジ…ムシャムシャ…」とネズミに噛まれる可能性がさらに高くなってしまいます。
じゃあ、露出した電線を見つけたらどうすればいいのでしょうか?
正しい対処法は、すぐに電気工事士さんに相談することです。
プロの目で見てもらい、適切な修理をしてもらうのが一番安全なんです。
「でも、すぐには呼べないよ…」という場合は、とりあえずその部分の電気を使わないようにしましょう。
安全第一で、専門家の助けを待つのが賢明です。
覚えておいてください。
電気の問題は見た目で判断できません。
小さな異常も見逃さず、プロの力を借りることが、家族と家を守る最善の方法なんです。
効果的な漏電対策と早期発見の方法
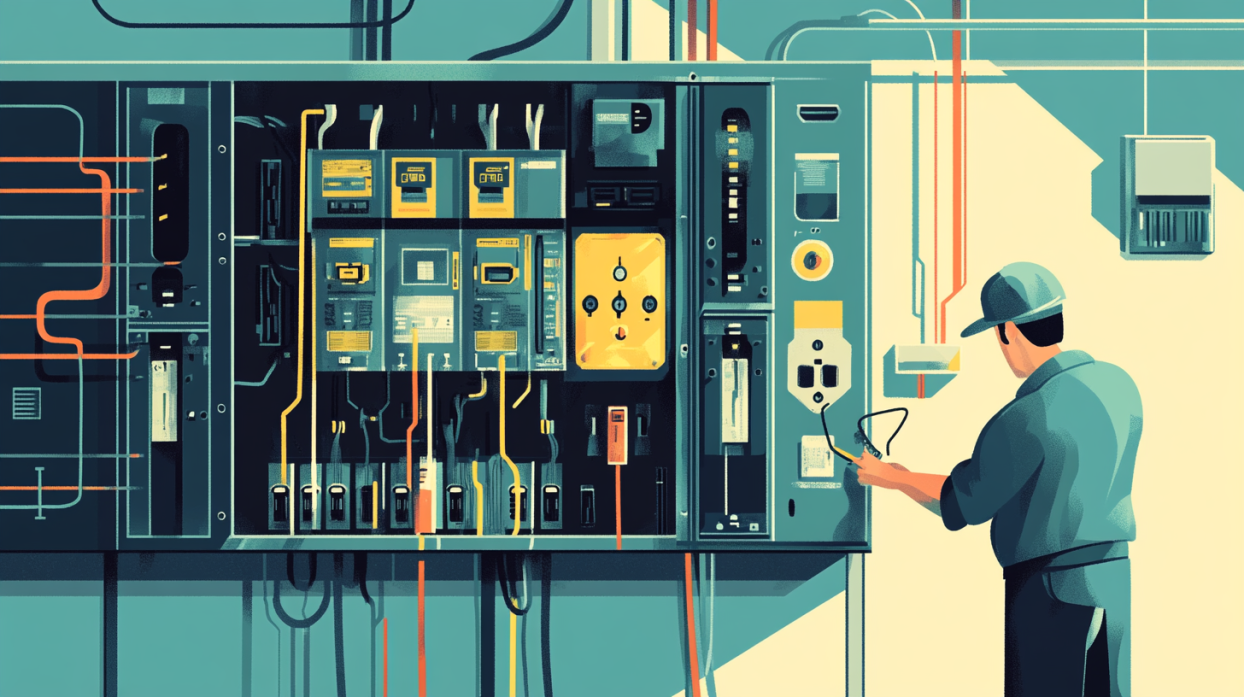
電線保護管の設置が有効!ネズミから配線を守る3つの方法
電線保護管の設置は、ネズミによる漏電を防ぐ最も効果的な方法の一つです。でも、どんな保護管を選べばいいのでしょうか?
まず、電線保護管の種類を見てみましょう。
- 金属製の保護管:丈夫で噛み切られにくい
- 硬質プラスチック製の保護管:軽くて扱いやすい
- 柔軟性のあるスパイラル保護管:曲がりくねった配線にも対応
実は、状況によって使い分けるのがコツなんです。
例えば、壁の中や床下など、ネズミの活動が激しい場所では金属製がおすすめ。
「カリカリ…ガジガジ…」とネズミが噛み付いても、びくともしません。
一方、目に見える場所や頻繁に動かす必要がある配線には、軽くて扱いやすい硬質プラスチック製が適しています。
「よいしょ…」と簡単に設置できるのが魅力です。
曲がりくねった配線や狭い場所では、柔軟性のあるスパイラル保護管が大活躍。
「くるくる…ぐにゃぐにゃ…」と自在に曲がってくれるので、どんな場所でも使えます。
でも、ただ保護管を取り付けるだけでは不十分。
隙間なく取り付けることが重要です。
わずかな隙間も、ネズミにとっては格好の侵入口になってしまうんです。
「えっ、そんな小さな隙間でも?」と驚くかもしれません。
でも、ネズミは体を平らにして、わずか1センチの隙間もすり抜けられるんです。
だから、保護管の継ぎ目や端部はしっかりと密閉しましょう。
電線保護管の設置は、少し手間がかかりますが、家族の安全を守る大切な投資です。
「よし、今度の休みにやってみよう!」そんな気持ちになりましたか?
ネズミから我が家の配線を守り、安心して暮らせる住まいを作りましょう。
漏電遮断器vsブレーカー!電気火災予防に重要な違い
漏電遮断器とブレーカー、似ているようで実は大きな違いがあるんです。電気火災の予防には、漏電遮断器の設置が非常に重要です。
「えっ、うちのブレーカーじゃダメなの?」そう思った方、多いんじゃないでしょうか。
実は、一般的なブレーカーだけでは漏電による火災を防ぐのは難しいんです。
では、どう違うのか見てみましょう。
- ブレーカー:過電流(使いすぎ)を感知して電気を遮断
- 漏電遮断器:わずかな漏電も感知して即座に電気を遮断
一方、漏電遮断器は「ジワッ…」というわずかな漏れ電流も見逃しません。
例えば、ネズミが電線をかじって小さな漏電が起きたとします。
ブレーカーは「ふーん、大したことないな」と見過ごしてしまいます。
でも漏電遮断器は「危険!」とピピッと反応し、即座に電気を止めてくれるんです。
漏電遮断器の反応の速さは驚くほど。
人間が「あれ?」と気づく前に、もう電気を遮断しているんです。
「ビリッ」という感覚さえ味わう暇がありません。
ただし、注意点もあります。
古い家屋では、漏電遮断器を後付けするのに工事が必要になることも。
「ウチ、築30年以上なんだけど…」という方は、電気工事士さんに相談するのがいいでしょう。
また、漏電遮断器を付けたからといって、油断は禁物。
定期的な点検は欠かせません。
「ちゃんと動いてるかな?」と思ったら、テストボタンを押してみましょう。
正常なら「カチッ」と音がして電気が切れるはずです。
漏電遮断器は、目に見えない電気の危険から私たちを守ってくれる、頼もしい味方なんです。
「我が家の守護神」として、ぜひ設置を検討してみてはいかがでしょうか。
壁からの異音に要注意!漏電の早期発見につながる5つの兆候
漏電の早期発見は、火災を防ぐ重要なポイントです。壁からの異音は、その重要な手がかりの一つ。
でも、他にもいくつか注意すべき兆候があるんです。
「え、他にもあるの?」そう思った方、安心してください。
ここでは、漏電の早期発見につながる5つの兆候をご紹介します。
- 壁からの「ジー」という異音
- 頻繁に落ちるブレーカー
- 電気器具の動作不良
- 壁のコンセント周りの変色
- 電気代の急激な上昇
「ジー」「ビリビリ」といった音は要注意です。
これは、電気が漏れて壁の中で放電している可能性があります。
「まるで小さな雷みたい…」と思ってください。
次に、頻繁に落ちるブレーカー。
「また落ちた!」とイライラしていませんか?
実は、これも漏電の兆候かもしれません。
ブレーカーが必死に私たちに警告を発しているんです。
電気器具の動作不良も見逃せません。
「テレビの画面がちらつく」「冷蔵庫が時々止まる」など、おかしな動きはありませんか?
これらも漏電のサインかもしれません。
壁のコンセント周りの変色も要チェック。
「あれ?こんな色だったっけ?」と思ったら要注意。
焦げたような色や、黒ずみは漏電の証拠かもしれません。
そして最後に、電気代の急激な上昇。
「今月の請求、高すぎ!」と驚いた経験はありませんか?
使用量が変わっていないのに電気代が急に上がったら、漏電を疑ってみる価値があります。
これらの兆候に気づいたら、すぐに行動を起こしましょう。
「よし、電気屋さんに相談だ!」という気持ちが大切です。
早めの対応が、家族の安全を守る第一歩になります。
日頃から気を付けて観察することで、漏電の危険から我が家を守れるんです。
「家族の安全は私が守る!」そんな気持ちで、毎日の生活を送ってみてはいかがでしょうか。
屋内配線vs屋外配線!被害リスクと点検頻度の違い
屋内配線と屋外配線、どちらがネズミの被害を受けやすいと思いますか?実は、屋外配線の方が屋内配線の2倍以上も被害を受けやすいんです。
「えっ、そんなに違うの?」と驚かれるかもしれません。
でも、これには理由があるんです。
まず、屋外配線と屋内配線の環境の違いを見てみましょう。
- 屋外配線:風雨にさらされ、温度変化が激しい
- 屋内配線:比較的安定した環境で保護されている
「ザーッ」という雨に打たれ、「ピカッ」という強い日差しにさらされ…。
こんな環境では、配線の劣化が早くなってしまうんです。
一方、屋内配線は快適な部屋で過ごしているようなもの。
「ふーっ」と安定した温度と湿度の中で、ゆったりと仕事をしています。
でも、これだけじゃありません。
屋外には別の危険が潜んでいるんです。
「ガサガサ…」という物音。
それは、屋外を自由に動き回るネズミたち。
彼らにとって、屋外配線は格好の遊び場であり、おやつなんです。
「ムシャムシャ…」と噛みつかれる危険性が、屋内よりもずっと高いんです。
だからこそ、屋外配線の点検はより頻繁に行う必要があります。
どのくらいの頻度がいいでしょうか?
- 屋外配線:少なくとも3か月に1回
- 屋内配線:半年に1回
でも、これくらいの頻度で点検することで、小さな問題を早期に発見できるんです。
点検のポイントは、被覆の傷や変色、ネズミの噛み跡などです。
「あれ?この配線、前はこんなじゃなかったな…」と感じたら要注意。
すぐに専門家に相談しましょう。
屋外配線の管理は少し手間がかかりますが、家族の安全を守るためには欠かせません。
「よし、今度の休みは屋外配線チェックの日にしよう!」そんな気持ちで、定期的な点検を習慣にしてみてはいかがでしょうか。
プラスチック被覆vs金属被覆!噛み付きやすさに5倍の差
電線の被覆、プラスチック製と金属製ではどちらがネズミに噛み付かれやすいと思いますか?実は、プラスチック被覆は金属被覆の5倍以上も噛み付かれやすいんです。
「えっ、そんなに違うの?」と驚く方も多いでしょう。
でも、これにはちゃんとした理由があるんです。
まず、プラスチック被覆と金属被覆の特徴を比べてみましょう。
- プラスチック被覆:柔らかくて噛みやすい、味や匂いがある
- 金属被覆:硬くて噛みにくい、味や匂いがほとんどない
「カリカリ…ムシャムシャ…」と噛むなら、やわらかくておいしそうな方を選びますよね。
そう、プラスチック被覆の方が魅力的なおやつになってしまうんです。
例えば、プラスチック被覆は歯ごたえがちょうどいい。
ネズミにとっては「おっ、これはいい歯磨きになりそう!」という感じなんです。
一方、金属被覆は硬すぎて「いてっ!」となってしまいます。
さらに、プラスチック被覆には微妙な味や匂いがあることも。
「んん?なんだかおいしそう…」とネズミの好奇心をくすぐってしまうんです。
金属被覆は味も匂いもほとんどないので、ネズミにとっては「つまんないなー」という感じ。
ただし、注意点もあります。
金属被覆だからといって、完全に安全というわけではありません。
特に古くなって劣化した金属被覆は、意外とネズミに狙われやすくなります。
では、どうすればいいのでしょうか?
- 新しい配線を引く時は、可能な限り金属被覆を選ぶ
- 既存のプラスチック被覆の配線は、金属の保護管で覆う
- 定期的に配線の状態をチェックし、劣化したものは早めに交換する
でも、少しずつでも対策を進めることが大切です。
家族の安全を守るため、我が家の配線の種類を確認してみませんか?
「よし、今度の週末は配線チェックの日にしよう!」そんな気持ちで、一歩一歩ずつ対策を進めていくことが、安心で安全な暮らしへの近道なんです。
電線の被覆の違いを知ることで、ネズミ対策の新しい視点が見えてきましたね。
「へぇ、こんなところにも秘密があったんだ」と、新しい発見があったのではないでしょうか。
この知識を活かして、我が家の電気設備を見直してみましょう。
小さな変化が、大きな安心につながるかもしれません。
家族の笑顔のために、今日からできることから始めてみませんか?
DIYで今すぐできる!驚きのネズミ対策と漏電防止法

ペパーミントの香りでネズミを撃退!配線周辺に設置する方法
ペパーミントの香りは、ネズミを寄せ付けない強力な武器です。この方法を使えば、簡単にDIYでネズミ対策ができちゃいます。
「えっ、本当にそんな簡単なの?」と思われるかもしれません。
でも、実はネズミは特定の香りが大の苦手なんです。
その中でも、ペパーミントの香りは特に効果的なんです。
では、具体的な方法を見ていきましょう。
- ペパーミントオイルを用意する(100%天然のものがおすすめ)
- 小さな綿球やティッシュにオイルを数滴染み込ませる
- 配線の周辺や、ネズミの侵入経路に設置する
- 2週間に1回程度、新しいものに交換する
実は、この方法には秘密があるんです。
ネズミの鼻は非常に敏感で、強い香りに耐えられないんです。
ペパーミントの清々しい香りは、私たち人間には心地よくても、ネズミにとっては「うぅ〜、くさい!」という感じなんです。
ただし、注意点もあります。
ペパーミントオイルを直接配線に塗るのはNG。
電線を傷めてしまう可能性があるんです。
「あっ、やっちゃった!」なんてことにならないよう、必ず綿球やティッシュを使いましょう。
この方法の良いところは、安全で自然なことです。
小さなお子さんやペットがいるご家庭でも安心して使えます。
「よし、今度の週末にやってみよう!」そんな気持ちになりませんか?
ペパーミントの香りで、ネズミを寄せ付けない快適な空間を作りましょう。
きっと、家族みんなが「あぁ、いい香り〜」と喜ぶはずです。
そして何より、ネズミによる漏電の心配から解放されるんです。
アルミホイルが強い味方に!電線を守る簡単ラッピング術
アルミホイル、実はネズミ対策の強い味方なんです。電線を守る簡単なラッピング術をご紹介します。
「えっ、台所にあるアレ?」そう、その通りです。
身近にあるアルミホイルが、ネズミから電線を守る頼もしい盾になってくれるんです。
なぜアルミホイルが効果的なのか、その理由を見てみましょう。
- ネズミは金属の味が苦手
- 噛んだときの音が嫌い
- 歯が立たずに諦めやすい
では、具体的な方法を紹介します。
- 電線の周りにアルミホイルを巻く(ゆるすぎず、きつすぎずに)
- 端をしっかり固定する(セロハンテープでOK)
- 定期的に点検し、破れていたら交換する
まるで、大切な宝物を包むように電線を守るんです。
ただし、注意点も忘れずに。
アルミホイルは電気を通すので、露出した導線に直接巻かないようにしましょう。
「ビリッ」なんて事故は絶対に避けたいですからね。
この方法の魅力は、すぐにできて、コストも抑えられることです。
「よし、今すぐやってみよう!」という気持ちになりませんか?
アルミホイルで電線をラッピングすれば、ネズミのいたずらから大切な配線を守れます。
これで、漏電の心配もグッと減らせるはずです。
家族の安全を守る、頼もしい味方になってくれるでしょう。
猫の気配で威嚇効果アップ!使用済み猫砂の活用法
使用済みの猫砂、実はネズミ対策の強力な武器になるんです。猫の気配を感じさせて、ネズミを寄せ付けない方法をご紹介します。
「えっ、使用済みの猫砂?」と驚かれるかもしれません。
でも、これが意外と効果的なんです。
ネズミにとって、猫は天敵。
その存在を感じさせるだけで、ネズミは「ひえ〜!」と逃げ出してしまうんです。
では、なぜ使用済みの猫砂が効果的なのか、理由を見てみましょう。
- 猫の尿の臭いが強く残っている
- ネズミは敏感な嗅覚で危険を感じ取る
- 天敵の存在を常に意識させられる
具体的な使い方を紹介します。
- 使用済みの猫砂を小さな布袋に入れる
- 配線の周りや、ネズミの侵入経路に置く
- 2週間に1回程度、新しいものに交換する
- 直接床に置く場合は、新聞紙などを敷く
まるで、見えない猫が見張り番をしてくれるようなものです。
ただし、注意点もあります。
猫アレルギーの方がいる家庭では使用を避けるべきです。
また、においが強いので、リビングなど人が多く集まる場所での使用は控えめにしましょう。
この方法の魅力は、コストがほとんどかからないことです。
猫を飼っているご家庭なら、今すぐにでも始められますね。
「うちの猫、こんな形で役立つなんて!」と、愛猫家の方はうれしくなるかもしれません。
使用済みの猫砂で、ネズミを寄せ付けない環境を作りましょう。
これで、配線をネズミの被害から守り、漏電のリスクも減らせます。
猫の力を借りて、家族の安全を守る。
素敵なアイデアだと思いませんか?
超音波でネズミを寄せ付けない!市販の発生器の選び方
超音波発生器は、ネズミを寄せ付けない効果的な対策です。目に見えない音波でネズミを撃退する、この最新技術の選び方をご紹介します。
「超音波ってどんな音?」と思われるかもしれません。
実は、人間には聞こえない高周波の音なんです。
でも、ネズミには「キーン!」と不快な音に聞こえるんです。
では、超音波発生器の選び方のポイントを見ていきましょう。
- 周波数範囲:20〜50kHzをカバーしているもの
- 電力:広い範囲をカバーするため、高出力のものを
- 設置場所:コンセントに直接差し込めるタイプが便利
- 追加機能:音量調整や間欠運転機能があると◎
- デザイン:部屋の雰囲気に合うものを選ぶ
実は、超音波発生器は日々進化していて、より効果的で使いやすい製品が次々と登場しているんです。
ただし、注意点もあります。
ペットの中には不快に感じる動物もいるので、ペットを飼っている家庭では事前に確認が必要です。
「うちの犬、急におかしな行動をし始めた!」なんてことにならないよう、気を付けましょう。
この方法の魅力は、24時間365日、静かに働いてくれることです。
「寝ている間も守ってくれるなんて、心強いな」と思いませんか?
超音波発生器を上手に選んで設置すれば、ネズミの被害から家を守れます。
電線をかじられる心配もなくなり、漏電のリスクも大幅に減らせるでしょう。
目に見えない音の力で、家族の安全を守る。
なんだか未来的な感じがしませんか?
辛さでネズミを撃退!ホットソースを塗る意外な活用法
ホットソース、実はネズミ対策に使える意外な逸品なんです。その辛さでネズミを撃退する、ちょっと変わった方法をご紹介します。
「えっ、食べ物のアレ?」と驚かれるかもしれません。
でも、この辛さがネズミにとっては天敵なんです。
ネズミは「ヒーッ!辛すぎる!」と逃げ出してしまうんです。
なぜホットソースが効果的なのか、その理由を見てみましょう。
- 辛味成分が口や鼻を刺激する
- 強い香りがネズミを混乱させる
- 舐めた後の不快感が学習効果を生む
では、具体的な使い方を紹介します。
- 市販のホットソースを水で2倍に薄める
- スプレーボトルに入れる
- 電線の周りや、ネズミの侵入経路に吹きかける
- 1週間に1回程度、塗り直す
まるで、辛い罠を仕掛けているようなものです。
ただし、注意点も忘れずに。
直接電線に塗るのは絶対NGです。
被覆を傷めてしまう可能性があります。
また、塗った場所が赤くなることもあるので、目立つ場所での使用は避けましょう。
この方法の魅力は、身近な材料ですぐに始められることです。
「よし、今晩からやってみよう!」という気持ちになりませんか?
ホットソースでネズミを撃退すれば、配線をかじられる心配もなくなります。
これで、漏電のリスクも減らせるはずです。
辛さの力で家族の安全を守る。
なんだか、料理以外の使い方を発見した感じがしませんか?
家庭内の調味料がネズミ対策の強い味方になるなんて、驚きですよね。